
Blue Blue Blue
一人暮らしを始めてちょうど一ヶ月目の今日は、朝からツイてない一日だった。
目覚ましはどういうわけか鳴らなかったし(きっと昨夜スイッチを入れ忘れたんだろう)、パンにはカビが生えてたし、冷蔵庫を開けて牛乳を飲もうとしたら、賞味期限が切れていた。
おまけにテレビをつけようとしたら、いきなり煙が出てくるし。
タダ同然で買った年季の入った中古品だから、寿命なんだろうけど、買い替えの費用とかを考えると頭が痛い。
そうでなくても、一人暮らしは金が掛かって仕方ないのに。
オレは憮然とした態度で家を飛び出して、手合いの開始2分前にギリギリ棋院に滑り込んだが、係りの人からもっと余裕を持って来て下さいね、なんて注意されてしまった。
息をつく暇もないままに、対局が始まって、結果は最後ヨセで追い上げられての半目負け。ここしばらくずっと、自己連勝記録を更新していたのが、あっけなくストップだ。
やりきれない気持ちを抑えて、帰りに電器屋でも寄ってくか、と外に出たら、いつのまにかどしゃぶりで、雷まで鳴っていた。
頭を抱えてその場にしゃがみこむと、後ろから聞き慣れた声が聞こえた。
「進藤、どうしたんだ、傘忘れたのか?」
「今日は午後から記録的な大雨になるって、天気予報で言ってたぞ」
振り返ると、そこには伊角さんと和谷が立っていた。
二人とも、手にしっかりと傘を持っている。
「朝起きたらテレビが壊れてて、ニュースも天気予報も何もチェックできなかったんだよ」
別に二人に恨みがあるというわけではないが、なんとなく恨みがましい目つきになりながら、オレは二人に言った。
「マジで? 大変だなー」
「そういえば、駅前の商店街の××電器で、テレビ特売してたぞ」
「伊角さん、それホント?」
「ああ。確か、昨日チラシが入ってた。確か、小さいやつだったと思うけど、5千円くらいで売ってた……ような気がする」
「オレそれ行ってくる!」
オレはすっくと立ち上がった。……が、目の前の雨はやはり勢いを衰えさせることなく、まるでオレの行く手を阻むかのように大きな粒となってアスファルトに打ち付けている。
オレは思わず和谷と伊角さんの方を見た。いや、正確には、二人の持っている傘を見た。
二人がたじろいだ。
「え、えーと……悪いな、進藤。オレたち、駅と反対側の方に行くんだ」
「他のヤツを当たってくれよ」
二人は、さして悪びれる様子もなく、傘を広げて雨の中に消えていった。
二人とも同じ方向に行くなら、一本傘を分けてくれたっていいじゃないか、と思ったが、雨はあまりにもひどくて、二人で一つの傘に入ってくれ、と言うのは、ズブ濡れになってくれ、と言うのと同じだったので、口に出すのはやめた。


オレはそれでも、誰か知ってるやつが通らないかなあとその場で待ち続けてみた。
が、一向に誰も現れない。
手合いのスケジュールを見に行ってみても、今日は誰も他に知り合いは来ていないようだった。誰かの忘れ物の傘とか、貸してくれないかなと受付にも行ってみたが、今日に限って傘は一本もないという。
「仕方ねーな……」
オレは覚悟決めた。雨の中を駆け抜けよう。どうせ傘があったって、濡れるときには濡れるんだ。
「せえの」
思い切って外に出た。雨は見た目よりももっと激しくて、突き刺さるような痛みが全身を襲った。
アスファルトの上は、全面水溜りのようになっていて、一歩進むたびに大きく水しぶきがあがる。
「あーもー、ホントになんなんだよ、この雨!」
オレはほとんど叫びながら、商店街に向かって一直線に走った。
商店街のアーケードに着いた頃には、全身もうグショグショで、下着までぴったり肌に張り付いて気持ち悪いくらいだった。スニーカーの中にも水が溜まっている。
軽くTシャツを絞ってみたら、まるで雑巾を絞っているかのように雨水がこぼれ落ちた。絞っても絞っても、どんどん水が落ちてくる。
「服着てプールに入ったら、きっとこんな感じなんだろーな」
オレはげっそりしながら独り言をつぶやいた。
「ま、いいや……。とりあえずテレビ買お」
店の前まで来ると、途端に騒がしくなった。どうやら大々的にセールをしているらしい。大雨にもかかわらず、客の入りはまずまずだった。
嫌な予感がした。
「すみません、ここでテレビ安売りしてるって聞いたんですけど!」
忙しそうに品物を棚に並べている店員を捕まえて訊いてみる。店員は愛想なく答えた。
「あ、特売のテレビは、もう昨日のうちに売り切れましたんで」
恐れていた答え。
「……やっぱり」
オレはうなだれて棚に寄りかかった。品物が濡れたら困る、と思ったんだろう。すぐに店員に、寄りかかるのはやめてください、と注意された。
あっちに通常価格のテレビがありますよ、と彼は親切にも教えてくれたが、ちらっと目をやると、プラズマテレビ十万という値札が目に入り、血の気が引いたオレはあっさり諦めることにした。
もう早く帰って、シャワー浴びてさっさと寝よう。
そう心に決めて走り始めたが、雨粒が目に入らないように下を向いていたのがいけなかった。
「きゃあっ」
突然何かが身体にぶつかって、同時に甲高い声が聞こえた。
オレはしりもちをついた。その瞬間、目の前で花柄の傘が転がっていくのが見えた。その向こうで、ぶつかった相手も盛大に地面に転がっていた。
「どこ見て歩いてるのよっ」
ぶつかった相手は、口うるさそうなケバイおばさんだった。
「すみません」
そっちこそ、どこ見て歩いてんだよ、と喉の奥まで出掛かったが、おばさんのあまりの迫力に気後れして、オレは言葉を飲み込んだ。
「ズブ濡れになっちゃったじゃない! あんたのせいよ! ちょっとこっちに来なさい!」
腕を掴まれ、屋根のある場所に強制的に連れ込まれる。クドクドと、耳が痛くなるようなお説教が始まった。おばさんはありえないほどしつこかった。
やれ最近の若者は注意が足りないだの、親の顔が見たいだの、挙句には近頃頻発している少年犯罪についてまで言及された。
そういった話には、終りがない。


タクシーを捕まえようとしたが、雨のせいかなかなか捕まらない。運良く空車のサインを見つけても、全身絞っても絞りきれないほどビショ濡れなせいで、乗車拒否をされてしまう始末だった。
さらに不幸なことには、やっとのことでめぐり合った親切なタクシーにいざ乗り込もうとした時、あるべき場所に財布がなかった。
どうやら、走ったり転んだりしてるうちに、どこかに落としてしまったらしい。財布の中には、今月の食費である現金4万5千円が入っていたはずだ。かつてないほど、全身の血の気が引いた。
悪夢だ。信じたくない。
激しく降りしきる雨の中、ボーゼンと歩いていると、トラックが勢いよく車道の端に溜まった水を跳ね上げて、頭から水をかぶるハメになった。どっちにしろもう全身濡れてるんだから、かまわないと言えば別にかまわないわけだが、それでもやっぱり腹だけはものすごく立った。
バカヤロー、となりふりかまわず叫んでやりたいくらいだった。
まったく、今日はどこまでツイてないんだろう。
これで風邪引いて肺炎にでもなったら、本気でシャレにもならない。
オレは、これ以上ないくらい惨めな気持ちで、坂を下った。
世界中の不幸が、みんなオレめがけて襲ってきているような気がした。
遠い道のりを結局すべて歩き通して、部屋に着いた頃には、雨はだいぶ小降りになっていた。
たとえようもなく暗い気持ちで鍵穴にキーを差し込んだが、鍵が開く手ごたえがない。
まさか、鍵をかけ忘れた?
いや、今朝鍵をかけたのは覚えてる。
おいおい、この上空き巣に入られたなんて冗談じゃねーぞ。
ドキドキしながらノブに手を掛け、ドアを開けると、目の前にはぴかぴかに磨かれた靴があった。
……塔矢だ。
塔矢が来てる。
「進藤?」


「塔矢」
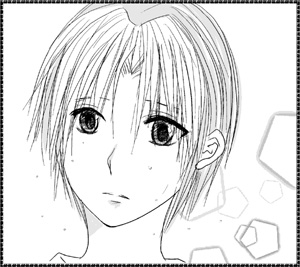

なんというか、塔矢の顔を見ると、途端にほっとしたような、疲れがどっと押し寄せてきたような、そんな気分になる。
「進藤、どうしたんだ! ズブ濡れじゃないか。……天気予報、見て行かなかったのか?」
「天気予報……テレビ、壊れてたから……」
「壊れた? ああ、あれはずいぶん古い型だったからな……。いや、そんなことはいいから、そこを動くなよ! 今、タオル持ってくるから」
オレが玄関先で呆然としている間に、てきぱきと勝手知ったる動きで、塔矢がバスタオルをクローゼットから出してくる。
「ほら、ふいて」
頭からタオルを被せられ、ごしごしと擦られる。
タオルはあっという間に水を吸って重くなり、絞るとやっぱり水が滴り落ちた。
「まったく、傘がないならタクシーで帰ってくればいいだろう」
「捕まらなかったんだよ。財布も失くしたし」
「財布を失くした?」
「うん」
「それは……大変だな。警察には届けた?」
「まだ」
「クレジットカードとか銀行のカードとか、入ってた?」
「カード……は、何も入ってない。現金だけ」
「そうか。じゃあ、金融機関に連絡はしなくていいな。後で一緒に警察に行こう。運がよければ返ってくるよ」
とにかくシャワーを浴びて、と塔矢がオレを促す。オレは言われるままバスルームに入って、熱いシャワーを頭から浴びた。
同じ液体なのに、さっきの冷たい雨とは全然違う感覚。
バスルームから出ると、洗面所の横に着替えがたたんで置いてあった。
首を通すとなんだか肌触りが優しかった。


やがて塔矢がオレの気配に気付き、不思議そうな顔でオレを見る。
「進藤、どうした?」
オレは首を振って笑った。
「なんでもない」
「…………?」
塔矢は首をかしげながら前を向き、鍋の火を弱めて、レタスを剥き始めた。とても手際が良かった。
塔矢は時々、こんな風にオレの部屋に来て、料理ができないオレのためにご飯を作ってくれる。
コンビニの弁当ばかり食べてたら集中力がもたないぞ、というのが塔矢の最近の口癖だ。
オレはそんな塔矢の背中を見ながら、ダイニングチェアーに腰掛ける。テープルに肘をついて、しばらくボーっとする。
そうこうしているうちに塔矢がオレの前に皿を並べ始め、あっという間に食事の用意が整った。
「いただきます」
二人で向かい合い、それぞれ手を合わせる。
少し薄味のこふきいもを口に入れながら、オレは今日あったことを思い返す。
最悪な一日だった。
嫌なことがたくさんあった。
「進藤、今日の対局はどうだった?」
塔矢が味噌汁をすすりながら、さらりと尋ねる。
オレは一瞬どきりとしながら、小さい声で答える。
「んー……。負けた」
「……そうか」
塔矢は変わらず穏やかな表情で、箸を口に運ぶ。
「何かあったのか?」
「え?」
「いや、なんとなく今日はいつもと違う感じがしたから。いつもなら、負けた碁だろうと勝った碁だろうと、もっと色々対局について話し出すだろう。『もっとああすれば良かった』とか『あのヨセが甘かった』とか」
「そうだっけ?」
「ああ。何か、嫌なことでもあった? 財布を落としたから、元気ないのか?」
それ以外にもあったよ、嫌なことありまくりだよ、とオレは口を開きかけたが、塔矢の顔を目の前にして、オレは言葉を失った。
朝寝坊したことも、半目差で負けたことも、大雨に降られたことも、テレビが壊れておまけに特売を逃してしまったことも、変なおばちゃんに長時間説教されたことも、トラックに水を撥ねられたことも、財布を落としたことも、突然大したことじゃないような気がした。
オレは自分のことを不幸だと思ったけど、オレには『おかえり』と言ってくれて、ご飯を作ってくれる人がいる。
落とした財布を一緒に探しに行ってくれる人がいる。
そしてきっと、今日あった色んなことに関する愚痴も、話せば黙って最後まで聞いてくれるんだ。
コイツはきっとまた、それは大変だったねって笑うだろう。
オレはお茶を一口飲んでから、改めて口を開いた。

「ホントに?」
「うん」
「……そんな感じじゃないけどな。帰ってきた瞬間のキミは、すごく悲壮な顔をしてたよ」
「おまえの思い過ごしだろ」
「そうかな」
「オレは幸せだよ」
「え?」
「うん、オレは幸せだ」
オレが強く頷きながら言うと、塔矢は首をかしげて、どうしたんだいきなり、らしくないな、とちょっと笑った。
オレも塔矢と目を合わせて笑った。
こんな風に笑って暮らせる日々が、オレを支えている。
一人じゃなくて、よかった。
「なあ、後で一局打とうぜ」
「その前に警察に行かないと」
「その後で! な? いいだろ?」
「なんだ、急に元気なったな」
「オレはいつでも元気だよ」
オレがにっと笑うと、塔矢は軽く息をついた。
「……そうだな、キミは元気だ。いつでも」
そう。
それがおまえのおかげだなんて、たぶん死んでも言わないけど。

警察に行こうと二人で外に出たら、空にはひとつ星が見えた。
俺は塔矢の手を取って歩き出した。
雨上がりの澄んだ空気が、火照った頬に当たる。

明日は、きっと晴れだ。

END